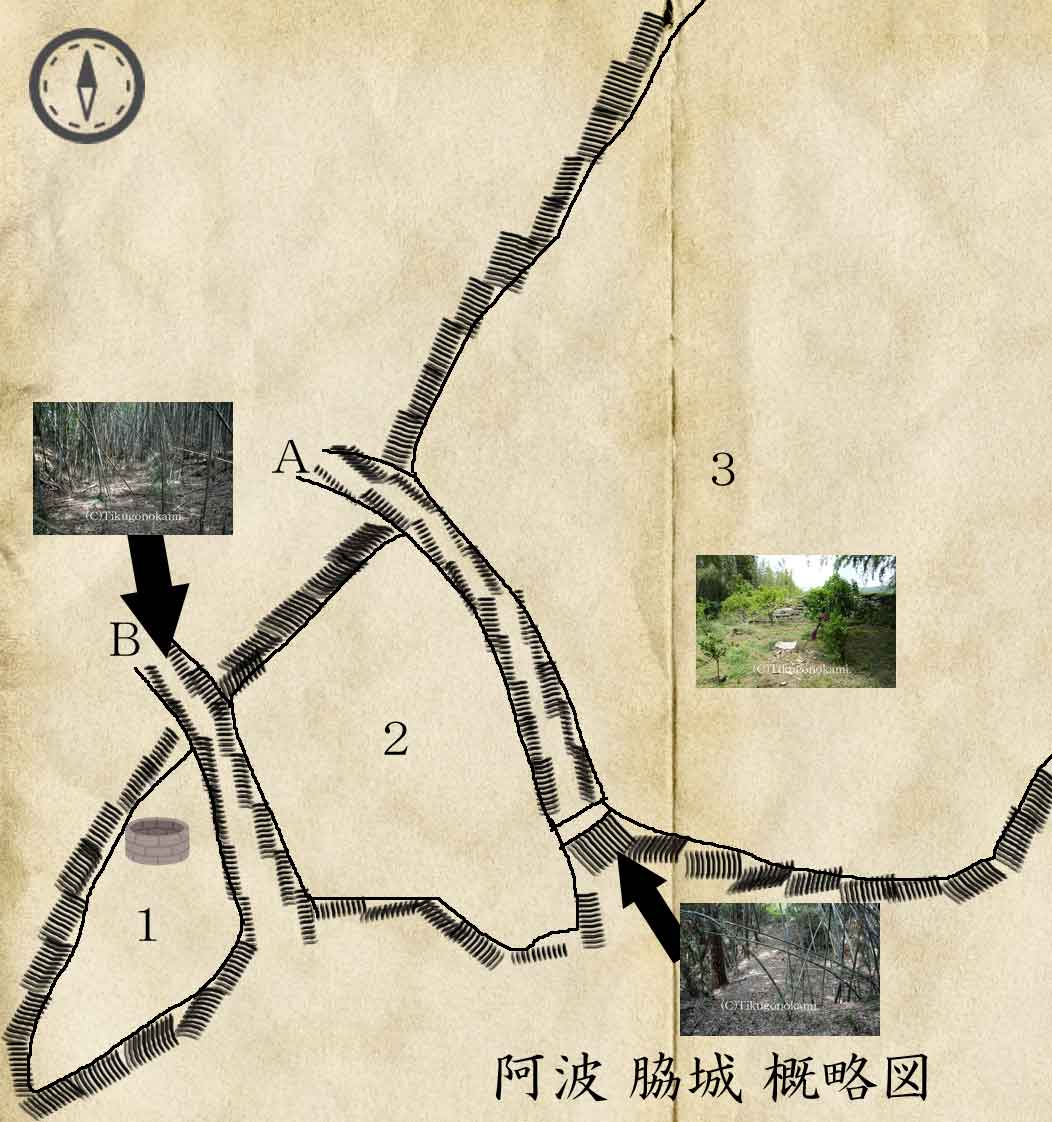●阿波 由岐城
住所:徳島県海部郡美波町西由岐(字東)
駐車場:なし
遺構:曲輪
標高:21メートル/比高:17メートル
由岐浦と土佐街道を押さえる位置にあるが、同じような立地条件にある牟岐浦や宍喰浦と違い材木の搬出ではなく船舶の寄港地としての役割が大きかったと思われる。現在は埋め立てられているが、当時は由岐港に面していたようだ。
築城年代は不明だが、城主は由岐隠岐守有興と伝わり、天正3(1575)年の長宗我部元親の阿波侵攻に際し降伏したという。しかし天正10(1582)年の中富川の戦いでは三好方として戦死した中に由岐善左衛門の名が上がっており、織田信長と元親の関係悪化に際し由岐氏は三好方に帰参していた可能性がある。その時に廃城になったという。現在は城山公園として整備されている。
城域の可能性が指摘されている公園の西に建つ西由岐八幡神社は天正17(1589)年の創建と伝わり、本祭で奉納される西由岐のうちわ踊りは県指定無形民俗文化財で阿波踊りの原型ともいわれる。
(由岐城と由岐港。港の沖で幕末に幕府軍と薩摩軍による阿波沖海戦が行われた)

(西由岐八幡神社。地図を見る限り、境内ではなく背後の後山が城だったのだろうか)

参考文献:徳島県の地名、三好一族と阿波の城館、現地の案内板、関西祭.com
感想:特にないです。