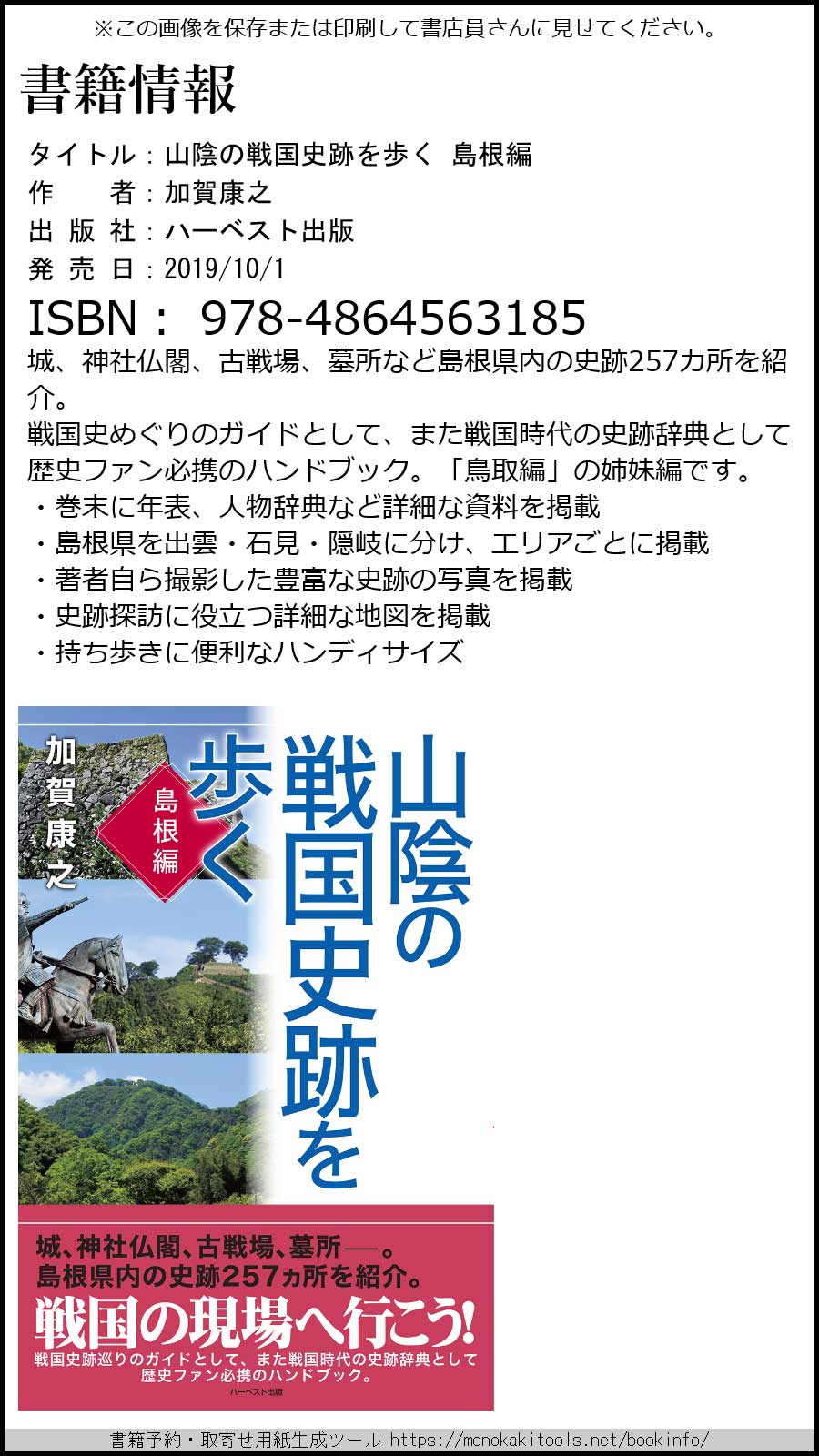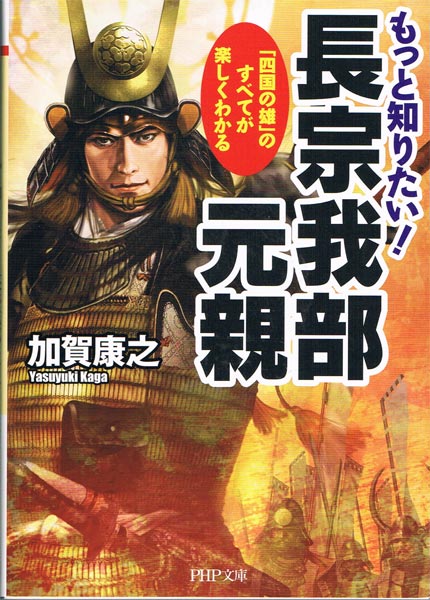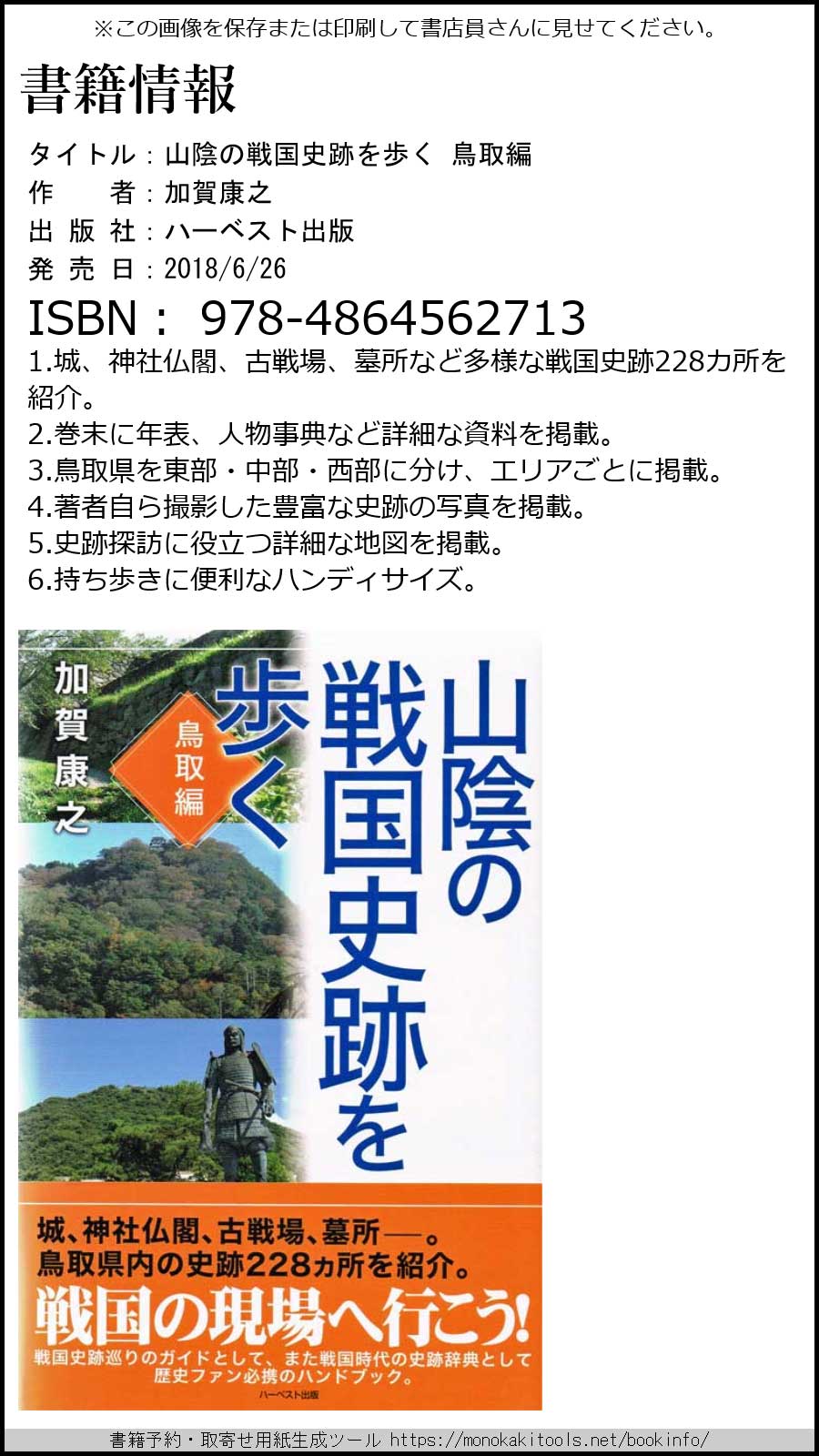「山陰の戦国史跡を歩く 島根編(ハーベスト出版)」を出版しました。全ての市と郡257ヶ所の戦国時代に関する史跡を写真付きで掲載しています。地図・コラム・年表・人物事典も充実しています。
山陰の書店と全国の地域史のコーナーに並んでいます。書店に置いてない場合は「ISBN:978-4864563185」でご注文下さい。金額は1800円+税となっております。
島根県内の資料館や博物館だと、安来市の「道の駅 広瀬・富田城」、松江市の松江歴史館、出雲市の古代出雲歴史博物館、大田市の石見銀山世界遺産センター、益田市の島根県芸術文化センター・グラントワ、で販売しているのを確認しています。
ネット通販でも購入できます。
・ハーベスト出版 公式サイト
・Amazon
・楽天ブックス
・セブンネットショッピング
・HMV&BOOKS online
・紀伊國屋書店 ※店頭受取可
・未来屋書店 ※店頭受取可
・honto
・e-hon
・TSUTAYA ※店頭受取可
・キャラアニ.com
・Honya Club.com
・Neowing
・ヤマダモール
・ブックオフオンライン(新品)
内容については公式サイトから立ち読みが出来ます。
・立ち読み_山陰の戦国史跡を歩く島根編
個人でもCMを作りました。ド素人の拙い動画ですので代わりに作って下さる方がおられたら、お会いした際にお菓子の詰め合わせくらいは御礼としてお渡しします。
「山陰の戦国史跡を歩く 鳥取編」も発売中です。島根県東部と鳥取県西部は密接な関係にあるため鳥取編も御購入いただけると理解が深まると思います。
令和時代に出た最初の島根県の戦国時代史跡ハンドブックです。御購入、何卒よろしくお願い致します。