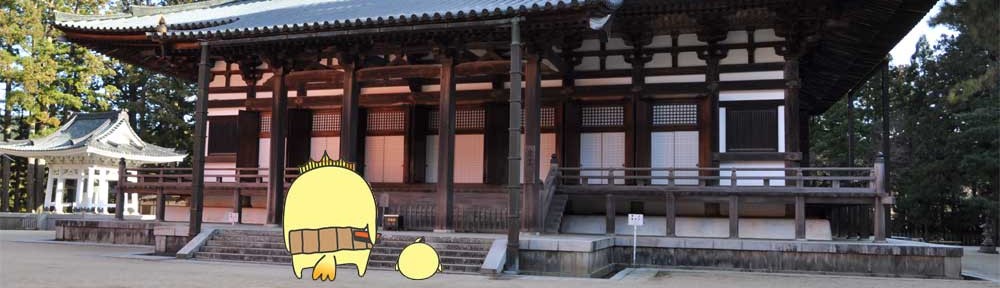●阿太加夜神社(あだかやじんじゃ)
住所:島根県松江市東出雲町出雲郷587(字 芦高)
駐車場:あり
主祭神は大国主命の御子・阿陀加夜奴志多岐喜比賣命。創建年代は不明だが出雲国風土記にも阿太加夜社として記載のある古社である。当地のある出雲郷はそのまま「いずもごう」と読まれていたが、阿太加夜神社があることから出雲郷を「あだかや」「あだかえ」と読むようになったという。
戦国時代には何度も出雲郷(阿陀加江郷)が出てきており、文明6(1474)年に尼子経久が京極政高から郷内の青木・多祢等を安堵され、享禄3(1530)年には多胡氏が取り上げた郷内の隠田を平浜八幡宮に寄進した。天正9(1581)年、鳥取城に向かう吉川経家が吉川元春と「あたかい」で会っている。近世には芦高社や芦高大明神と呼ばれていたが、明治維新後に阿太加夜神社に改名した。
10年に一度行われる松江城山稲荷神社と阿太加夜神社の間を神輿が船で往復する松江ホーランエンヤは日本三大船神事の一つで松江市の一大イベントになっている。
(兵庫神社。堀尾氏の松江城築城の際、一箇所で何度も石垣が崩れたため松岡兵庫頭が地鎮祭を行ったところ積み上げることができた。後年、兵庫頭が祀られたのが兵庫神社である)

(日清・日露戦争に従軍した出雲郷出身の軍人を讃えた表忠碑。昭和3(1928)年に建てられた)

(神社の西を流れる意宇川に河童がいたという。橋は河童橋と名付けられている。河童の頭石に水をかけると災難から逃れられるという)

(国引きの碑。神社から数百メートルの場所で国引き神話の締めが行われた。神話の内容を書くと長くなるので省略)

(令和元(2019)年に行われた大橋川でのホーランエンヤの様子)

参考文献:明治神社誌料:府県郷社 中、島根県の地名、出雲尼子史料集 上巻、新鳥取県史資料編古代中世Ⅰ 古文書編下巻
感想:神社もいいのですが、やはりホーランエンヤは勇壮で一生に一度は見ておきたい船神事です。次回の2029年も見に行く予定です。