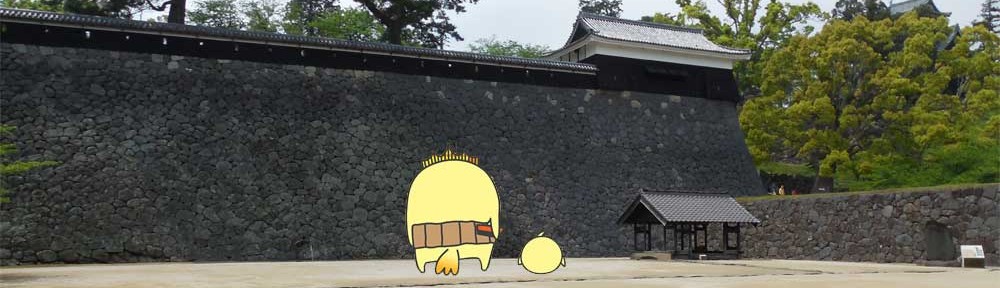●備中 幸山城(高山城、甲山城)
住所:岡山県総社市西郡・清音三因
駐車場:あり
遺構:曲輪、堀切、土塁、土橋
標高:159メートル/比高:-43メートル
『備中府志』には延慶年間(1308~11年)に庄左衛門四郞資房が築城し、応永年間(1394~1428年)に備中守護・細川氏の被官だった石川氏が城主になったという。天文22(1553)年の幸山表の戦いで三村家親に属していた渡辺盛忠は敵の荒木七郎三郎を討った。永禄10(1567)年、明禅寺合戦で城主の石川久智は三村氏に属したため宇喜多直家の軍勢によって戦死している。
元亀2(1571)年1月には毛利家は尼子再興軍らと手を結んで対抗していた浦上宗景の攻撃に備え栗屋就方らを守備に向かわせたが2月には落ちた。しかしその後、石川久智の跡を継いだ石川久式と毛利軍の活躍で奪回されている。天正3(1575)年、石川久式は毛利氏に反旗を翻した三村元親に付き敗北したため自害。城は毛利氏の支配下となり、天正5(1577)年に宇喜多直家を援護するため湯浅将宗を幸山城に向かわせた。この頃、毛利氏は拡張工事を行っている。天正10(1582)年の羽柴秀吉による備中高松城攻めでは小早川隆景が在城した。その後、備中が宇喜多秀家の領地になると幸山城は直轄となったが慶長5(1600)年の関ヶ原の戦いで秀家が改易されると廃城になる。
(中央にある三日月の形をしている曲輪の南側(堀切などがある方向)から撮影。土塁の外側にある自然の石を利用しているようだ)

参考文献:岡山県中世城館跡総合調査報告書 第2冊 備中編、岡山県の地名、現地の案内板
感想:福山城に行く途中、看板が見つけて行ってみました。
比高がマイナスになっているのは和霊神社から降って行ったからです。結局、登って戻らないといけないのでマイナス・プラスどちらでも一緒ですが。