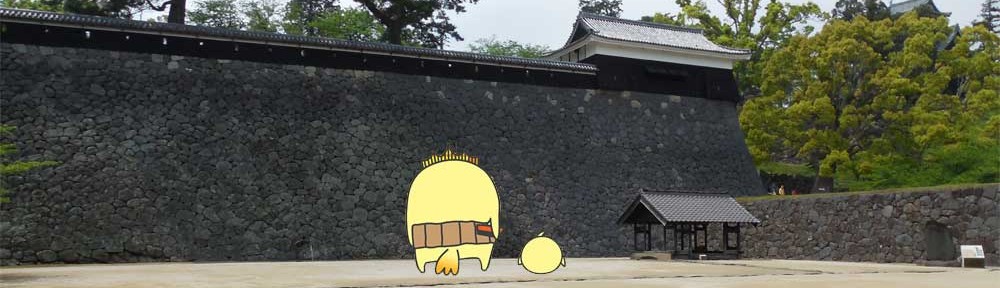●常陸 江戸崎城
住所:茨城県稲敷市江戸崎(字 城山)
駐車場:不明
遺構:曲輪、土塁、空堀
標高:22メートル/比高:18メートル
稲敷台地の南に突出した場所にあり、東西の地名が荒沼、沼田であることから周囲は湿地帯だったと思われる。鎌倉時代の初期には小田氏の家臣が居住していたが、嘉慶元(元中4、1387)年頃に関東管領・上杉氏の被官だった美濃の土岐原秀成が当地に入り永享年間(1429~1441年)頃に築城したという。
土岐原秀成は信太庄(しだのしょう。稲敷市、土浦市などの一部)惣政所職を掌握し、その他にも勢力を広げていった。天文12(1543)年頃には土岐原から土岐に改姓する。関東管領・上杉氏の元で戦い、上杉氏の没落後は小田氏と組んで佐竹氏らに対抗する。だが小田原の北条氏についたため、天正18(1590)年の小田原攻めの最中、土岐治綱は豊臣秀吉の家臣・浅野長吉の軍勢に降伏して治綱は退去した。
その後は佐竹義宣の弟・芦名盛重が入るが慶長7(1602)年で佐竹氏が出羽に移封されるとその後入った大名にも使われたが、やがて廃城になったという。
(古城開運稲荷神社。往時は土岐氏の守護神が祀られていたが天正18(1590)年の滅亡と共に衰退する。明治17(1884)年に町民の願いによって再建された)

参考文献:茨城県の地名、現地の案内板、茨城名勝誌、茨城県の中世城館
感想:北側の江戸崎小学校も城址だったのですが入っていません。