平成20年9月9日(火)、急な休みが出来たので史跡巡りに出かけることにした。今年、東海北陸自動車道が開通して愛知県から富山県まで高速道路が完全に繋がったので、富山県に決定。
ほとんど渋滞もなく10時には富山県の魚津市に到着。
1:越中天神山城・・・魚津市小川寺にある。1582年4月、勢いに乗る織田勢は大軍で魚津城を包囲した。その際、救援しようとした上杉景勝が陣を構えたことで知られている(って現地の案内板には書いてあったけど知られているのか?)。現在は魚津市歴史民俗資料館などが建っている。
中腹まで車で行けるので楽。土塁なども多少残っていた。

(中腹に建つ何とか博物館の4階から見た魚津市街。景勝はこの城から織田の大軍を見て無念の思いを抱いたことであろう)

2:魚津城・・・魚津市本町1丁目にある。織田軍に対抗するため、景勝が修築した城。越中西部の要衝だった。上記の通り、織田軍に包囲された。上杉景勝は救援に向かったが、同盟国の武田勝頼が滅ぼされて信濃も織田軍の領地となり、春日山城を窺う姿勢を見せたため、景勝は泣く泣く撤退した。見捨てられた魚津城は本能寺の変の翌日に玉砕。現在は大町小学校などが建っている。
遺構などは特になかった。碑が校内にあったので学校に連絡してから行った。小学校の授業中にデジカメ持ってうろうろしてたら明らかに不審者と勘違いされるからな。

3:(おまけ)米騒動発祥の地・・・魚津市の海岸にある。魚津城からすぐ近くにあったので行ってみた。ちなみに分かっていると思いますけど大正の米騒動の方です。
4:猿倉城・・・富山市舟倉にある。飛騨の塩谷秋貞が越中進出のために築城した。その後、織田・上杉と飛騨の三木氏が奪い合った。最終的には豊臣秀吉の家臣・金森長近に落とされ、役目を終えた。
今は何も残ってなく碑があるのみ。山頂に風の城という展望台が建っており、景色を眺めるには最高の場所。
5:富山城・・・富山市本丸にある。1543年に神保氏の家臣によって築かれ、以来神保氏の居城となった。しかし1576年に上杉謙信によって落とされ、織田と上杉の争奪の場となるが、謙信没後の混乱をついて織田軍が富山城を攻略。佐々成政が城主となるが、本能寺の変後に豊臣秀吉に逆らい肥後に移封となったため、前田家に与えられた。以後、明治維新まで前田家が越中支配の居城として使用した(焼失により30年ほど使われない時期を除く)。現在は富山城跡公園となっている。
現在は整備のため工事中だったので、何となく消化不良気味だった。特に見られない場所があったとかってわけじゃないけど、車両などがたくさんあるとしらけてしまう。
石垣・堀などは当時のものだったので、ここは見所があった。

6:尻垂坂古戦場・・・富山市西新庄にある。1572年に上杉謙信と一向一揆軍の間で行われた戦いの古戦場跡。ここにある地蔵尊を縛るとマラリアが治るという言い伝えがある。
民家の中にあり分かりづらかった。近所の方も例によって「知らない」との答えばかりだったので。

次の目的地に移動する途中、二車線の道の右側を走っていたら信号を過ぎたタイミングで「ウ~~!」というサイレンが聞こえて後ろから白バイが・・・。しかし「お前は邪魔だから左に寄れ」という白バイ隊員のサインがあったので、どいたところ、二つ前に走っていたバンが捕まっていた。何が理由だったか知らんが、捕まるかどうかなんて紙一重だよなあ・・・。
7:本覚寺・・・富山市婦中町富崎にある。神保氏の菩提寺。ここにある鐘は富山城の鐘よりよく響いて、紛らわしかったため、砂を焼き付けたと言われている。
実際に鐘を見たが・・・良く分からなかった。

8:安田城・・・富山市婦中町安田にある。国指定史跡。豊臣秀吉が越中を攻めた際、前田家の家臣が布陣した。
縄張りが分かりやすいのはいいんだけど・・・復元されすぎていて不自然。伊豆山中城を思い出した。

9:白鳥城・・・富山市吉作にある。南北朝時代にも使用されたと言われているが確かではない。戦国時代、神保氏が上杉家の備えのため、富山城の出城として築いたのが定説となっている。豊臣秀吉が越中を攻めた際、豊臣秀吉がここに本陣を構え、降伏した佐々成政を引見した。
山頂まで車で行ける。遺構が良く残っており、ここから見える景色も良い。

本日はこれでお終い。ホテルに向かった。
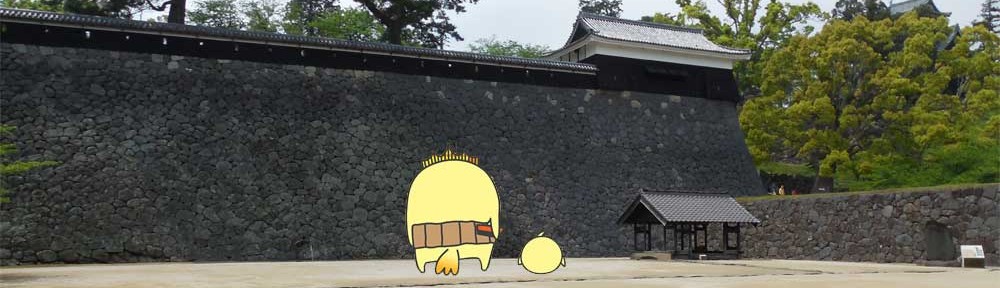



>柳葉さんへ
尻垂れって言葉は気になりますよね・・・。分かります。
昔は日本にもいろんな感染症がありましたが、衛生状態の改善などでかなり減ったようです。
マラリアと聞くと私は太平洋戦争のニューギニアが最初に頭に浮かびます。
そうだったんですか!
「しりたれざか」・・垂れって気になりますね。(すみません。)
(ーー;)一度聞いたら忘れられない地名です。
由来がありそうですね。(すごいネーミングなので。)
マラリアの件も知りませんでした。(確かに南の国・・というイメージでしたので、何でかな?と思ってました。ありがとうございます。)
>柳葉さんへ
このモニュメントは1年半前に出来た新作(?)です。
尻垂坂は「しりたれざか」です。何か逸話があるのかもしれませんね。
マラリアは南の国の感染症のようなイメージがありますが、「おこり」と呼ばれ日本でもありました。現在は他の感染症と同じで撲滅され、国内での感染例はないようです。
>キヘイジさんへ
魚津城の戦いの頃は上杉家滅亡の危機でしたから、景勝は「俺も後から行くぞ」という悲壮な気分だったじゃないでしょうか。
春日山城って新潟県の左端にありますよね。地理が分からなかった頃は「謙信や景勝はなぜ信濃を重要視したんだろう」と思っていましたが、地図見たら一目瞭然でした。
>ゆうさんへ
この日は快晴でした。それを狙って出かけたんですが。
高知から富山は移動が大変出そうですね・・・。
なんと・・。米騒動のモニュメントもあるんですね・・(^^;)俵!!
天気も良くてよかったですね☆
尻垂坂古戦場・・
マラリア治癒のなんですか???(日本なのに?)
「しりたれざか」と読むのでしょうか、初めて知りました(^^;)
>魚津城
そうなんですよね〜、変の翌日に玉砕っていうのがまた悲しいんですよ。
この城があるのとないのとじゃ(しかも玉砕)、精神的にも戦略的にも違っていたでしょうからね。
信濃は春日山城のまさに喉元ですから、魚津城を見捨てるのは仕方がないんですけどねえ。
きれいですね。
今年の女性会議は富山です。
しかし、高知から40人もの女性を連れて行くのは・・・
今年は休み頂きました。
現在歴史の資料づくりを学んでいます。
その学習の日になってましたので、やめました。
でも、本当は行ってみたかったですね。