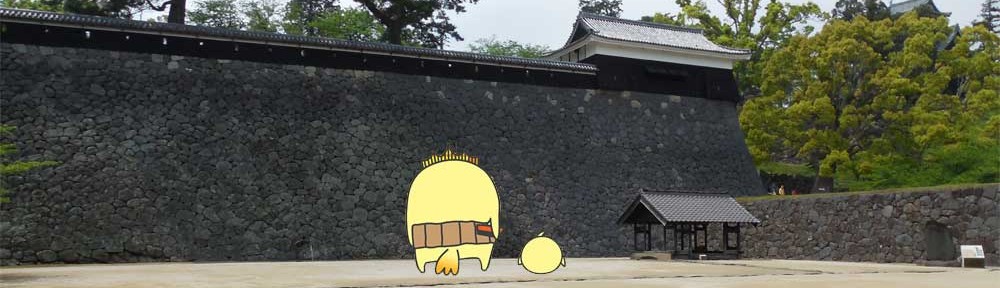平成21年3月8日(日)、宮崎県南那珂郡南郷町の宿から出発。
68.鵜戸神宮・・・日南市大字宮浦にある。鵜戸崎の洞窟の中に鎮座している。由緒など詳しいことは公式ページをご覧ください。またここは剣法発祥の地として知られ、相馬四郎義元が「念流」を、愛州移香が「陰流」を御神示を受けて会得したと言われている。
洞窟の中に本殿がある変わった神宮社。朝早く来たのに若い人も含めて結構観光客がいた。
69.飫肥城・・・日南市飫肥十文字にある。築城年代は不明。1458年に島津氏が伊東氏に備えて、一族を備えに入れたことが記録に残っている。その後、島津氏・伊東氏の争奪戦の舞台となった。1577年に伊東氏が日向から追われると島津氏の所有となったが、九州攻めで島津氏が降伏した後は明治維新まで伊東氏が城主となっている。石垣などが現存している。
テレビで見て、なんとなく気になっていた城。周りの武家屋敷なども含めて雰囲気が良い。
この日はちょうど「人力車サミットin飫肥」が行なわれていて、人力車に無料で乗れたらしい(私は利用していないけど)。
70.伊東家墓所・・・日南市飫肥大字楠原にある。飫肥城主・伊東氏歴代の墓所。
案内も何もなく分かりづらい。神社の奥にある仁王像が目印。
71.祝吉御所跡・・・都城市早水町にある。島津忠久が鎌倉より下向して館を構えた場所。忠久は最初「惟宗」姓を名乗っていたが、地名を取って島津と名乗った。故にここが島津家発祥の地と言われる。
・関之尾公園(関之尾の滝)・・・都城市横市町にある。
72.都城領主館跡・・・都城市姫城町にある。都城領地の政治的中心は都之城だったが、一国一城令で廃城となったため、城主の都城島津家は領主館に移った。遺構は特にない。
73.都之城(鶴丸城)・・・都城市姫城町にある。都城島津家(北郷氏)が1375年に築城した。天正年間に一時、移封されたが、1600年に都城島津家が城主に復帰。一国一城令で廃城となった後は、都城領主館に移った。現在は城山公園となり、歴史資料館が建っている。
特に見るべきところはなかった。
これで宮崎県は終わり。次は宮崎県全域を廻ってみたいな・・・。これから鹿児島空港に向かいつつ残った史跡を廻る。