2011年12月29日(木)、山陰帰省のついでに香川県に寄った。最近、讃岐の諸将に興味が出てきたので・・・。
1.昼寝城・・・さぬき市前山。東讃で活躍した寒川氏の居城。昼寝をしていても落ちないほどの堅城であることから昼寝城と名付けられたという。その名の通り、阿波の三好長治の二度の攻撃を退けている。当城を長治が攻めている隙に長宗我部元親は手薄になっていた阿波南部への侵攻を開始している。
感想:現地の案内板には「長宗我部元親によって落とされた」とあったが、元親は堅固なこの城を見て「こんな城、攻めるのは時間の無駄だ。他の城を落とせば自然に落ちる」と言って無視したはず。落とされた、というのはそのことを言っているのかな?
工事か何かで入り口が閉鎖されていたため、遠くから眺めて終わった。
2.大窪寺・・・さぬき市多和兼割96。四国霊場第八十八番札所。行基の開基。空海が奥の院の岩窟で求間持の法を修め、お堂を建てたのが始めといわれる。百を越す堂塔があったが長宗我部元親侵攻の際の兵火で悉く焼失した。
感想:寺の案内通り「長宗我部軍の兵火で・・・」と書いたが、実際には1574年の三好長治による昼寝城攻めの際に雑兵によって焼かれていた(『長尾町史』より)。なので元親とは関係がない。
そして元親の紹介はいつものようにぼろくそ。「土州の渠魁(盗賊、悪漢などの首領)」。相変わらずの人気だ。
ここはお遍路で最後(結願)のお寺。お遍路をしている人がここに来ると感慨深いものがあるのだろう。
3.大櫟城・・・さぬき市大川町田面。長宗我部元親が雨滝城攻略の際に陣営となった。現在の豊田神社の境内一帯だったと伝わっている。
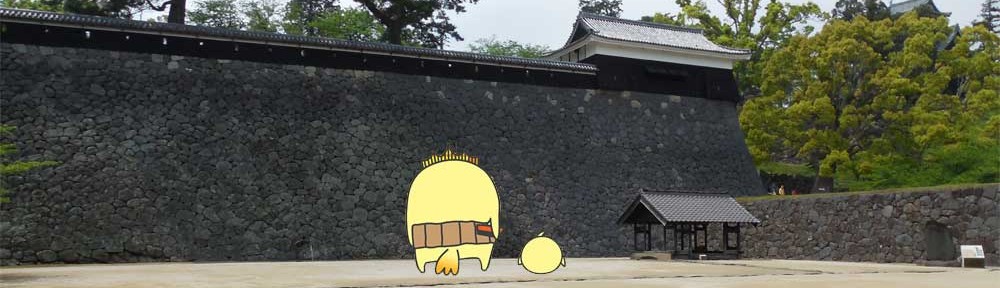






大窪寺も南海治乱記では三好が香西攻めから阿波に撤退する際に昼寝城を攻めたが落ちず、寒川に味方した大窪寺を焼いたとなっています。
寺が江戸時代に由緒として書いた大窪密寺記にも長宗我部が来る前の時代に焼かれたと書いてあるのですが、寺にある案内板はこの大窪密寺記を転記しつつ長宗我部が焼いたと改竄して書いてあります。
大窪密寺記から100年ほど後にやはり大窪寺で書かれた大窪寺記録という書物では昼寝城を攻めた長宗我部が大窪寺を焼いたとこれも改竄しています。
ちなみに専門家によると長宗我部が昼寝城を攻めたということはないそうです。
昼寝城を攻めてその時に寺を焼いたのは先に書いたとおりに南海知乱記では三好であり、寺などが三好を長宗我部に置き換えて伝えているということがわかります。
長宗我部元親は阿讃予で寺社を焼きまくったことになってますからね。四国霊場第八十八番札所の番組でも「廃仏毀釈と元親は霊場の敵」と言われていましたし。
昼寝城ですが、『秋山家文書』をもとに三好に敗れた寒川氏が元親についたという説があるみたいですね。讃岐は史料がなさ過ぎて分からんことが多いです。
>saさん
そうですね。元親が侵攻した頃にはあまり価値がなかったようですね。
黒田官兵衛が植田城を無視したのはよく知られていますが、元親が昼寝城を無視した話もあったような気がするんですよね・・・。
元親は昼寝城は攻めてませんね。昼寝城自体、有効利用されていたのが三好氏全盛期で、元親は接触自体無かったはずです。
「こんな城、攻めるのは時間の無駄だ。」というのは黒田官兵衛が四国攻めの際に、元親の築いた讃岐植田城に関して残した言葉のような。