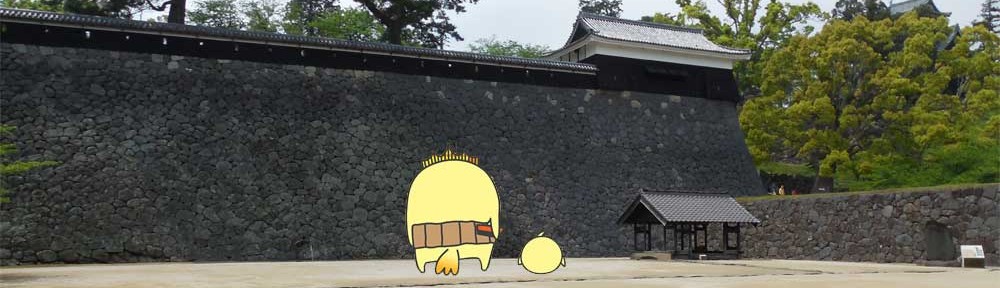住所:愛知県刈谷市野田町東屋敷62
祭神は品陀和気命など。676年に創建された。1300年に修築される。1548年と1554年の兵火により荒廃するが、刈谷城主・水野氏が造営し祈願所とした。その後、当地を治めた板垣氏、三浦氏、土井氏、板倉氏の崇敬を受ける。
毎年8月に行われる『野田雨乞笠おどり』は刈谷市の無形民俗文化財に指定されている。社宝に水野勝成奉納の総髪の兜がある。
(刈谷市駅の近くにある『みづ乃』で買ったかつなりくんクッキー)

感想:刈谷市美術館で催された『刈谷城築城480年記念展』に寄ったついでに行ってみました。記念展では総髪の兜も展示されていました。